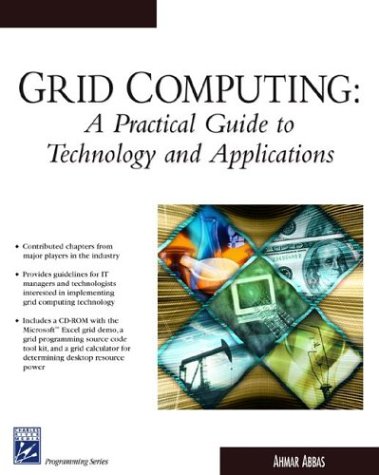2005年02月
2005年01月
2004年11月
2004年10月
2004年09月
2004年08月
2004年07月
2004年06月
2004年05月
2004年04月
2004年03月
2004年02月
2004年01月
2003年12月
2004年04月19日
「ここがおかしい!」と言えるサラリーマンになる!
最近読んだ本で、これは参考になる!!と思った本があったので紹介する。長い間、会社で働いているとこれは「おかしい」と思うようなことがあっても、言わなくなったり、感覚が麻痺してしまったり、問題から目をそらしてしまったりして、折角の成長の機会を逃していることが少なからずともあると思い、どうすればよいか考えたいと思ったのが本書を購入しようと思ったきっかけである。
読んで見ての感想は、具体的な例が書かれていて大変分かり易かった。「なぜ?」と疑問を持ち続ける事及び行動を起こす事の重要性が協調されていた。基本に帰って見直しを行いたい人にはピッタリの本である。
Amazonの紹介文より転載:
柴田昌治が仕事で成功する知恵をあなたに贈る!
自分の持つ可能性を開花させ、「働きがい」と「成功」を手にしたい。
そう願うあなたに向けて、大ベストセラー『なぜ会社は変われないのか』の著者、柴田昌治氏が、仕事で成功する知恵をわかりやすく伝授します。ここ数年で、企業が求める人材像は急激に変わりました。今までの方程式では解けない新しい課題や問題が渦巻いています。自分の明日の姿をどう描いて、「生き方」「働き方」の方向を決めればいいのか、悩んでいるかたも多いことでしょう。本書では、「問題をいかに発見し解決するか?」「人と協力し合って自分を生かすには?」など、労働市場でのあなたの価値を高め、しかも大きなやりがいを持てる働き方を解説しています。自分の「生き方」「働き方」を前向きに見つめ直したみなさんに、ぜひ読んでいただきたい1冊です。
目次:
第1章 何が問題なのかを発見し、解決する知恵とは?
第2章 “どうしたら勝てるのか”豊かな発想をもたらす知恵とは?
第3章 本当に役立つ情報を集めて生かす知恵とは?
第4章 明日のシナリオが描ける人材になる知恵とは?
第5章 人と協力し合って自分を生かす知恵とは?
第6章 仕事をやりがいのあるものにする知恵とは
2004年01月04日
Grid Computing
グリッドコンピューティングに関する本格的な本が遂に出ました。408ページにわたってグリッドコンピューティングの概念、歴史、実装などが詳細にわたって書かれています。グリッドコンピューティングは、次期に注目されているプラットフォーム技術の1つで(インター)ネットを介して接続した複数のコンピュータで仮想的に高性能コンピュータをつくり、利用者はそこから必要なだけ処理能力や記憶容量を取り出して使うシステムのことです。
Grid Computing: A Practical Guide to Technology and Applications (Programming Series)Amhar Abbas (著), Ahmar Abbas (著) 価格: ¥4,634
発売予定日は 2004/03/01 で現在予約受付中だそうです。目次は以下の通りです。
SECTION I: CONTEXT
Chapter 1: Infrastructure Evolution
Chapter 2: Productivity Paradox
Chapter 3: Disruptive Technology
Chapter 4: History of Grid Computing
SECTION II: TECHNOLOGY
Chapter 5: What is Grid Computing?
Chapter 6: "Discovering and Managing Grid Services"
Chapter 7: Grid Security Paradigms
Chapter 8: OGSA (Grid + Web Services)
Chapter 9: Standards
Chapter 10: Sensor Grids
Chapter 11: Data Grids
Chapter 12: Peer to Peer Computing
Chapter 13: Desktop Grids
Chapter 14: Internet Computing
Chapter 15: Cluster Computing
Chapter 16: Hive Computing
Chapter 17: Globus
Chapter 18: High Performance Computing
Chapter 19: Grid Programming Techniques
Chapter 20: Managing Grid Environments
Chapter 21: Grid Networks
SECTION III: APPLICATIONS
Chapter 20: Application Assessment
Chapter 21: Grid Portals
Chapter 22: Gaming
Chapter 23: Utility Computing
Chapter 24: Financial applications
Chapter 25: Oil and Gas Applications
Chapter 26: Application Integration
Chapter 27: Enterprise Applications (CRM/ERP)
Chapter 28: Telecommunications
Chapter 29: Manufacturing
Chapter 30: Life Sciences
Appendix A: On the CD-ROM
2003年12月26日
質問力
2003年度の流行キーワードということで気になって以下の本をGetした。amazonによると、「質問力」のキーワードでは1位だそうだ。amazonによると評価は2分される。丁寧すぎでかったるいという人もいれば、具体的で分かり易いという人もいた。私は後者の方だ。読みやすくて1日で読み終わった。
簡単に言うと質問力は、コミュニケーション技術の1つで、知りたい情報を引き出すテクニックの1つであると、私なりに解釈した。一番参考になったのが、最後の方の宇多田ヒカルと「アルジャーノンに花束を」の本で有名なダニエル・キイスの対談だ。クリエイティブな「質問力」というテーマの例としてこの対談を上げているのだが、2人共ニューヨーカーとあって、刺激の多い=インスパイアする質問を連発していた。読んでいて心地よかった。このような質問が出来たら・・・と思った。全体的に例が多くて分かり易くてよかったと思う。
また、キリストと弟子との対談には、このような質問力の実践がいくつか載っていると言う事で例が書かれていた。2000年程前にもう既にこのようなことが実践されていたということが分かり、更に聖書に親しみを覚えた。

blog@yuiとLocalscopeの所に詳しい本の紹介が載っていたので転載する。・・・
☆ 斉藤孝『質問力 話し上手はここがちがう』(blog@yui)
=======================
「質問力」に関してまず大切なのは、聞き方がうまければ、自分に実力がなくても面白い人のおもしろい話が聞きだせるということだ。質問が面白ければ、人はどうしてもおしえてあげたくなってしまう。
これを私は「教育欲」という造語で呼んでいるが、「教育欲」が動き出す最低限の「質問力」
を身につければ、仕事に初めてついた時でも上の人からよい情報を得ることができるだろう。
=======================
☆ 質問力
=======================
・いい質問とは「具体的かつ本質的」なもの。質問は「意識」してすべきである
・相手に共感して深める「沿う技」、「ズラす」を活用する。
ポイントはここいらだと思うのですが、これがどう行われているかについて、多くの実例をもって示しています。たとえば、「黒柳徹子×淀川長治」、「古田敦也×周防正行」などといった対談について、分析して、「この質問が、この答えを引き出しているのだ」と説明してくれています。
=======================